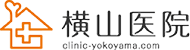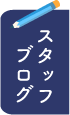骨粗鬆症は、骨の密度が下がり骨折しやすくなる疾患です。骨の中がスカスカになり、ちょっとした転倒や、明らかな外傷がなくても(いつの間にか骨折)骨折しやすい状態となってしまいます。日本での患者数は約1000万人以上といわれており、高齢化に伴ってその数は増加傾向にあります。
骨粗鬆症が原因で起こる骨折には主に、背中が丸くなってしまう圧迫骨折や、寝たきりにつながる大腿骨近位部骨折などがあり、これらは生活の質を大きく低下させてしまい、場合によっては寝たきり状態になってしまいます。また、一度骨折してしまうと、再度骨折するリスクが非常に高まってしまいます。(ドミノ骨折)そのため、骨粗鬆症は早期診断・早期治療が非常に重要です。
健康寿命を延ばすためには骨密度の測定を定期的に行い、必要であれば早期に治療を介入することが重要です。寝たきりになってしまう前に、日常生活の質をできるだけ長く維持していきましょう。
原因と病態
骨粗鬆症の原因
- 1.加齢
- 年齢を重ねるとカルシウムの吸収が悪くなったり排泄が増えたりすることで、骨を形成することが出来にくくなります。
- 2.閉経
- 閉経に伴いエストロゲンが低下すると、骨が破壊される細胞が活性化され骨密度が低下します。
- 3.運動不足
- 骨を強くするためには、骨への適度な刺激が重要です。運動不足になると骨にカルシウムがうまく蓄積されず、骨粗鬆症となってしまいます。
- 4.ステロイドの
長期服用
- ステロイドは骨に作用して骨形成を抑えてしまい、骨吸収を亢進させることで骨粗鬆症を著名に進行させてしまいます。
- 5.喫煙
- 5.タバコはカルシウムの吸収を悪くさせ、エストロゲンの働きを弱めるため骨密度が低下していきます。
- 6.他の疾患
- 糖尿病、関節リウマチ、副甲状腺の病気、腎機能障害・透析などの疾患は骨粗鬆症と大きな関連があると言われています。骨粗鬆症の治療とともに、それぞれの治療が重要とされています。
これらの原因で骨粗鬆症が進行してしまいます。原因を理解することで普段からの予防にもつながります。
診断
骨粗鬆症の検査では、骨密度を測定します。測定の方法は様々ありますが、当院では骨粗鬆症学会でも推奨されているデキサ法(2重エネルギーX線吸収法)を用いて骨密度を測定しています。
また、身長が低くなってきている・背中が曲がってきているなどの症状がある方は、胸椎・腰椎のレントゲンを撮影し、すでに圧迫骨折がないかを確認していきます。
さらに血液検査をすることで、現在の骨の代謝(骨形成・骨破壊)のバランスを確認したり、ビタミンDやビタミンKの充足度を確認したりして治療薬選択に役立てます。
予防と治療
骨粗鬆症の予防には食事・運動・日光浴が重要とされています。

-
1.食事
カルシウムだけでなくビタミンDやビタミンKなどバランスよく摂取することが重要です。

-
2.運動
ウォーキングやランニングなどの運動が望ましいですが、身体機能が低下している方でウォーキングが困難な方は、簡単な長続きできる運動をしていくことが重要です。例えば、何かにつかまりながら片足立ちしたり、踵落とし運動などがあります。
どのような方でも怪我せず継続することが重要です。

-
3.日光浴
夏場では10~20分、冬場では30~50分程度日を浴びることで皮膚からビタミンDが生成されます。
治療薬は主に4つの種類に分けられます。
- 1.骨代謝を調整する薬
- 活性型ビタミンD3製剤、ビタミンK2薬、カルシウム製剤
- 2.骨破壊を止める薬
- ビスホスホネート、SERM、抗RANKL阻害薬
- 3.骨形成を促進する薬
- 副甲状腺ホルモン薬
- 4.骨形成を促進し、
骨破壊を止める薬
- 抗スクレロスチン抗体薬
これらのように様々な種類の骨粗鬆症治療薬がありますが、それぞれの状態に合わせて最適な治療薬を選択していきます。